

ある日の夏の夕暮れ
夏の始まり。戦後ドイツを代表する芸術家アンゼルム・キーファーの生涯と現在を追ったドキュメンタリー『アンゼルム “傷ついた世界”の芸術家』を観た。劇中で、アンゼルムはアトリエの壁に“存在の耐えられない軽さ”と記し、こう続ける。「人は“重さ”を避けて“軽さ”を求める。(中略)地球の歴史や宇宙の歴史など歴史を通してみると我々は雨粒にも満たないことが分かる。雨以下の原子なのだ。それなら当然言える“我々は軽い”」と。

『アンゼルム “傷ついた世界”の芸術家』(全国公開中)
その言葉が妙に残り、テキストの由縁であろうミラン・クンデラ著『存在の耐えられない軽さ』を読み始めることにした。初めてその秀逸なタイトルに触れたのは、フィリップ・カウフマン監督の映画を通してだったと思う。当時はまだ中学生だか高校生で、大人の恋愛が描かれた映画なのだろうぐらいにしか分からなかったように思う。
舞台は68年のプラハ。多くの女性と関係を持ち自由を愛する医師のトマーシュと地方の小さな町出身のウェイトレス、テレーザを主軸とした物語だ。原作本はまだ途中だが、映画を改めて見直してみるとテレーザの写真を撮るという行為が印象的に残る。「プラハの春」の弾圧を目の当たりにし、引き裂かれるような思いの中、彼女は必死にシャッターを切り続ける。そうすることで現状を、「生」を、受け入れようとしていったのであろうと映った。
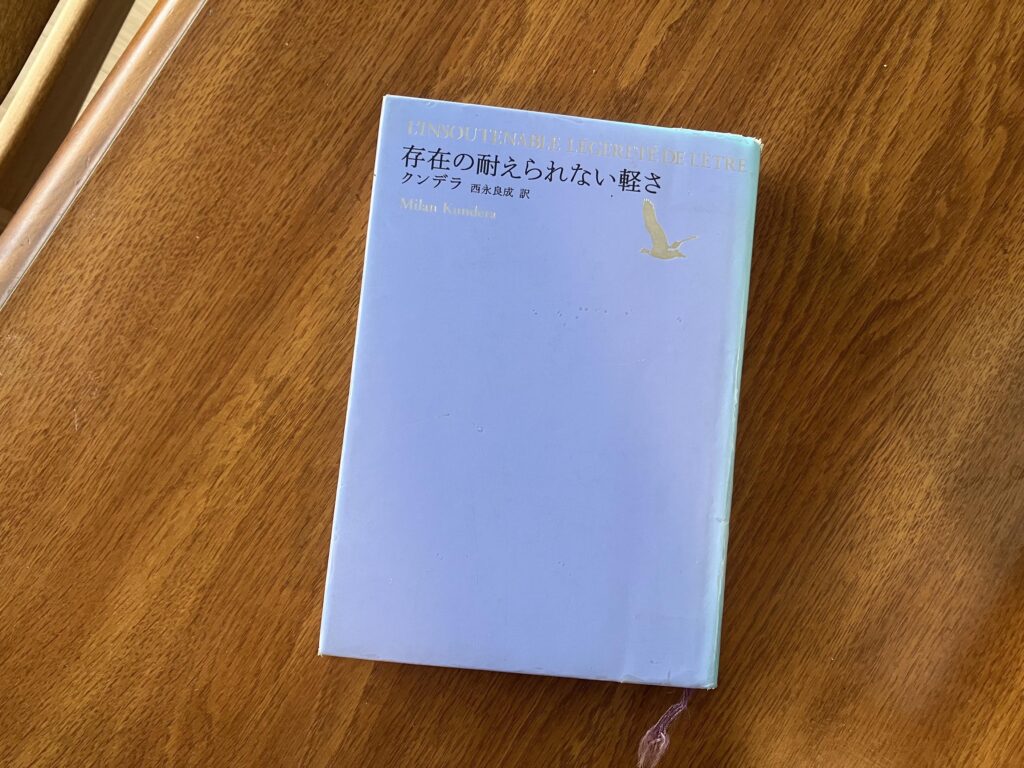
ミラン・クンデラ『存在の耐えられない軽さ』
軽さというものは妙だと思う。おそらく誰しもが物心ついた頃、初めて宇宙に放り出された自身の存在の軽さに気付きとまどい、存在とは何か、なぜ生きるのかという根源的な問いに出会う。宇宙の中にいま「いる」ということを、なにより自分でたしかめていたいと思う心理はとても人間的で面白い。
『存在と時間』の著者、ドイツの哲学者ハイデガーの存在論へと思考を巡らせる。もちろん、とても壮大な哲学で私にはとうてい深い理解には及ばない。でもなんとなくだけでも感じるようなところはある。存在の中に潜む有限的な「生」について。この世に生まれた瞬間から、世界と関係することで「存在」がある。産声とともに、すべての事象において、終わりがあることを知りながら、私たちは瞬間的に生き続けていく。

ある日の夏の公園
「神は死んだ」というニーチェの言葉によってこの世に永遠がないことを知る。ニーチェはさらに言う。「永劫回帰という思想はこのうえなく重い荷物だ」と――。『存在の耐えられない軽さ』の文中に興味深い一文がある。「(前略)荷物が重ければ重いほど、それだけ私たちの人生は大地に近くなり、ますます現実に、そして真実になるのである」。
死ぬことを前提に生きる。そのとても耐えがたい無情さを思う。思いながらも、『存在の耐えられない軽さ』でテレーザが「生」を写真におさめることで救われていくように、そのことは同時に希望的でもあるように思える。心底うだるような灼熱の夏。梅雨の終わりとともに、あたりまえに夏を告げ、鳴き続ける蝉の声に包まれながら。
※写真すべて筆者撮影
ヤマザキ・ムツミ
ライターやデザイナー業のほか、映画の上映企画など映画関連の仕事に取り組みつつ暮らしている。東京生活を経て、京都→和歌山→熱海へと移住。現在は再び東京在住。

